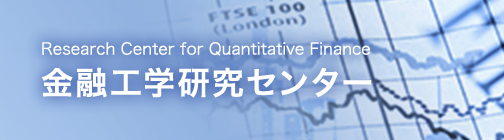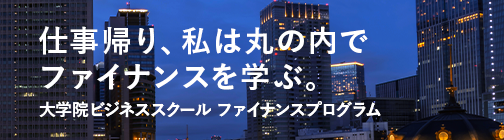修了生の声
高橋 友輔
旭化成ファーマ株式会社 旭化成医薬科技(北京) 有限公司 董事長兼総経理
理論に立ち返る MBA への挑戦
会社で組織構造改革やマーケティング戦略策定プロセスの再構築に携わる中で、「戦略」や「組織」といった経営の根幹に関わる論点に直面する機会が増えました。専門書やセミナーを通じて学びは続けていたものの、得られる知識はどこか表面的・断片的で、限界を感じるようになっていました。実務にすぐ役立つ“明日使える知識”ではなく、それらを支える理論に一度立ち返ってみたい―――そんな思いから、体系的に経営を学び直す必要性を強く感じ、 MBA取得を志しました。
都立大を選んだのは、理論を追求するのに最適な修士論文の執筆がカリキュラムに組み込まれていたことに加え、経営組織論や戦略論といった関心領域の教育が充実していると感じたためです。さらに、社会人にとって通いやすい立地や学費の手頃さも、大きな後押しになりました。
論理を磨いた2年間、そしてその先へ
入学後、1年目は授業を通じて、学問として経営に向き合う姿勢や、研究を進めるための基礎として、論文の正しい読み方や考え方から徹底的に叩き込まれました。2年目には自らの研究テーマと向き合い、関心領域の原著論文を丹念に読み込みながら構想を深めていきました。担当教員の先生には、ロジックを何度も見直すよう指導いただき、一文一文に意味を持たせるまで推敲を重ねました。厳しくもありましたが、その分、論文を書き上げたときの達成感はひとしおでした。会社において、それらの学びを基にした組織・戦略変革提案では、自身の言葉にも説得力が増したと実感しています。余談ですが、卒業研究の内容を日本マーケティング学会で発表する機会を得て、ベストオーラルペーパー賞をいただくこともできました。理論に触れ、自分で思考し、“かたち”にしていったこの2年間の経験は、知識以上の財産として自分の中に残っています。
池田 晋平
証券会社 公開引受部勤務 マネージャー
入学の動機
私は証券会社において企業の株式上場を支援する部署に在籍しています。企業が株式を上場するには、安定した事業の成長と上場企業として情報開示や不正を起こさせない内部管理体制の構築等が求められます。よって、その支援をするには、金商法や取引所規則の理解、並びに法務、会計、ファイナンス、ガバナンス等の幅広い知識が求められます。テクニカルな知識は巷に溢れる書籍等を読めば身に着けることができるかもしれません。しかし、不確実な世の中において事業の成長性を理解する力をいかに培うかは難しいテーマだと感じていました。また、上場を果たすまでには年単位のプロジェクトになることが通常であり、その間、関係者との間で必ずしも正解のない議論をすることがよくあります。そこで常に求められることは論理的な思考力と周囲を納得させるための伝える力です。
大学院入学時はコロナ禍でした。40代後半の私に残された時間軸の中でいかにキャリアに向き合うべきか考えた故のひらめきが東京都立大学MBAへの進学でした。何もしなければ時間が単に過ぎることが明らかである中、ここに進めば前に進むための道が開けるのではないかと。
理論と実践の往復から「前へ」
本学には専任教員の下で入学者に深い学びを提供するための豊富なカリキュラムが用意されています。また、少数精鋭である中、ダイバーシティを地で行っており、学生は年齢、男女、職業全てバラバラでした。但し、皆社会人であり、学びに真摯であるという点においては共通でした。学びに年齢は関係なく、私自身も一回り以上年下の仲間と多くのテーマで議論を重ねることで大いに刺激を受けました。
修士論文は、会計不正とガバナンスをテーマにしたものを執筆しました。私は学部時代に論文を書いたことがありませんでしたが、論文執筆にあたっては、実務界でも高名な先生から直接ご指導を受ける機会を得ました。先行研究を読み込み、リサーチスペースを見つけ、仮説を構築し、収集したデータを統計分析した上で考察する研究は、容易に結果が見えない中で探索を繰り返す、およそ楽な作業ではなかったものの、限られた時間の中で一定の成果をまとめることは今振り返ってもとても貴重な経験となりました。
大学院に通ったからと言って必ずしも道が開けることはありません。机上で理論だけを学んでも意味がないと思います。理論と実践を往復することで、先の見えない不確実な時代の中で前に進むことができるのではないかと思います。また、大学院を修了しても学びに終わりはありません。前に進むために学び続けること、これが、私が本学で学んだ一番重要なことだったことかもしれません。
本田 亮
富士通コネクティッドテクノロジーズ株式会社 サービスイノベーション事業部
自分の将来を具体化するラストチャンス
私は工学系の大学院を修了して大手電機メーカーに就職し、将来に不安を抱くことがないまま研究活動や製品開発に邁進してきました。しかし、市場は変化し事業構造も変えていかなければならない時代を迎えています。私自身も事業統合や分社化を経験し、新規事業創出や投資家視点での判断が現場に強く求められるようになってきたことに不安が募っていきました。また、ジョブ型雇用の導入や企業内高齢化の対応など人事制度や雇用制度も変えていかなければなりません。組織行動論や人的資源管理の知識を体系的に学び、自分自身をアップグレードしなければならないという想いが高まっていきました。加えて、年齢を重ねるにつれて公共活動や社会貢献を意識するようにもなっていきました。「自分の将来を具体化するラストチャンス」という決意をし、公立大学である東京都立大学大学院のビジネススクールの門を叩くことを決めました。
現実の課題に論理的に対処する実践力の養成
修士論文を書き終えて感じたことは、「修士論文の執筆は、問題を深く考え抜き、説得性のある理論を構築する訓練である」ということでした。振り返ると、当初の研究計画書で描いた課題は漠然としている一方で、近視眼的に結論を導こうとするアプローチが見え隠れしたものだったと思います。1年以上にわたる研究において、専門書や先行研究論文を読み込み、最新の調査データや統計データから事実を一つひとつ拾い上げ、事実から問いを掘り下げることによって、仮説を説明する理論のフレームワークを作っていくプロセスを学びました。ゼミでは「手がかりを見つけること」、「事実に潜む問いに気づくこと」を丁寧に指導いただきました。修士論文の事例インタビューのシナリオは理論を裏付けるための具体化された内容となりました。このプロセスは講義では得られないものです。実際のビジネスシーンでは不確実な事態への対応が求められます。修士論文の執筆では、学術的な意義に加えて現実の課題に論理的に対処する実践力が少なからずとも養われたと思います。
近藤 倫子
大手電線メーカー 組織:経営企画室 IRグループ
経営学という武器を身に付けたい
近年、IRを取り巻く環境は劇的に変化しています。特にコーポレート・ガバナンス、気候変動対策、人的資本など、開示が求められる分野は拡大の一途をたどっています。私もIR担当としてESG情報の開示に取り組んできましたが、人的資本や知財など無形資産の価値を定量化し、投資家に説得力のある形で提示するための理論的裏付けと分析力が不足しており、 説明責任を十分に果たせていないのではないかという課題を抱えていました。
そんな折、経営戦略やコーポレート・ガバナンスに関する書籍と出会い、課題解決には経営に関する幅広い知識が必要だと痛感し、MBAへの挑戦を決意しました。
都立大大学院は少人数教育を強みとしており、最先端の研究を行う教員や多様なキャリアを持つ学生と議論を重ねることで、思考力と実践力を高められると考え、入学を志しました。
二年間で得たこと、残った課題
入試時に提出した研究計画書では、ESG活動が企業価値に与える影響を分析することを修士論文のテーマに掲げていました。しかし、授業で多様な論文を読むうちに当初のテーマが漠然としていることに気付き、最終的には社外取締役の在任期間と企業価値の関係を分析することにしました。論文執筆と仕事の両立は想像以上に大変でしたが、論文の執筆をする中で、感覚的に捉えていた課題を理論とデータで検証できる“武器” を手にできたことは大きな財産です。
一方、執筆過程で自らの知識不足も痛感しました。二年間では経営学の広大な領域を網羅するには時間が足りず、とりわけ理論の実証に不可欠な因果推論の深い理解には課題が残りました。MBAは修了しましたが、実務で得た疑問を研究につなげ、その成果をIR戦略につなげていく好循環を構築したいと考えています。学びには終わりはないという先人の言葉を胸に、大学院で得た知見を祖に、自己研鑽を続けていきたいと思っています。