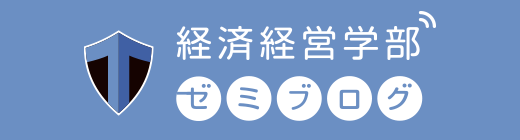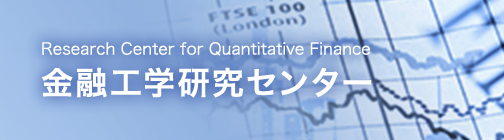ゼミ紹介
2年生の終わりに、3年生から所属するゼミ(演習)を選択します。
様々なテーマのゼミが開講されており、8割以上の学生が所属しています。
テーマからゼミを探す
- 経済学・統計学を通じて社会を見つめる
- ミクロ経済学: 理論とその応用
- 歴史的アプローチからみる経済・経営・産業
- 産業革命について再考する
- 実証ファイナンス
- Rによるデータ解析
- 経済学の古典を読む
- 経済学、特に応用計量経済分析の最新の研究に触れる
- 日本の歴史から考える経済と経営
- イノベーションの事例分析
- アジア経済史、アジア経済論
- ファイナンス
- 行動意思決定論
- マーケティング・サイエンスによるデータからの知識発見
- 財務会計
- 管理会計に関わる研究テーマについて自分の手で研究を行うこと
- 途上国における国際経営戦略
- マクロ経済学と金融論
- 経営のプロフェッショナルになる
- マーケティング戦略
- リスクとリターンの統合評価
- テキストマイニング
- オペレーションズ・リサーチによる問題解決
- ミクロ経済学・ゲーム理論
- マクロ経済学
- ゲーム理論を学ぶ
開講されているゼミの一覧
- 教員詳細情報を確認することができます。
- リサーチマップの詳細を確認することができます。リサーチマップの詳細はこちらから。
- ミニ講義の詳細を確認することができます。
経済学・統計学を通じて社会を見つめる |
基本的な経済理論と統計学を使って社会の仕組みや問題を考えます。3年次は統計学と計量経済学、R・Python・gretlなどの統計ソフトの使用法、論理的な文章の書き方を学びます。4年次は各自の興味に応じて、経済学的アプローチから研究を行います。 |
|---|---|
ミクロ経済学: 理論とその応用 |
消費者や生産者の最適化行動、市場均衡といった理論分析のほか、ゲーム理論の寡占市場への応用分析をゼミ共通のテーマにしています。このなかから、毎年みな思い思いのテーマで卒業論文をまとめています。 |
歴史的アプローチからみる経済・経営・産業 |
関心のある経済・経営事象について、基礎的な経済理論・経営理論を身につけつつ、経済史等の歴史学の先端的議論を十分に参照した上で、その未来を構想します。3年次にはチームごとに関心テーマ(国内外の経済社会の動向、産業史など)について研究を進め、その成果を学外で発表、4年次には個人の関心に基づいて自由にテーマ選択し卒業論文等を執筆します。 |
産業革命について再考する |
産業革命は、地球温暖化の原因の一つで物質的豊かさの源でもあります。私たちは、産業革命を理解し適切に関わってきましたか。演習では、図書館を活用し、産業革命の文献・資料について、自ら読み・考え・研究し、報告・議論し、論文を書く力をつけていきます。 |
実証ファイナンス |
ファイナンス理論・金融工学について学び、金融市場や投資,財務活動などに対する科学的思考を養います。 |
Rによるデータ解析 |
3年次に統計学やデータ解析に関する本を輪読して理論の理解を深め、4年次前半に各々興味のある分野でデータ解析に関する論文を検索・紹介することにより論文のスタイルに慣れ、4年次後半に自らデータ解析を行い、論文を執筆します。データ解析には統計ソフト「R」を用います。 |
経済学の古典を読む |
基本的な経済理論を意識しつつ、古典の読解に取り組むことで経済学の歴史を学びます。古典には様々な情報が(妥当とは言えない主張や論理的に整合しない記述も)含まれていますが、それらと批判的に向き合うことでテーマを発見し、各自の問題意識にもとづき研究を進めます。 |
経済学、特に応用計量経済分析の最新の研究に触れる |
このゼミでは、最新の応用計量経済分析論文を取り上げ、一般向けに要約した記事を読みます。American Economic Review誌のウェブサイトには図表コーナーがあり、そこから選んだ図表を統計や計量経済学の視点で解説し、経済学的重要性も考察します。最終的には日本の事例や応用可能性を考え、データ収集や実証分析を進め、卒業論文の執筆に繋げます。 |
日本の歴史から考える経済と経営 |
近世後期から昭和初期(19世紀後半から20世紀半ば)ころまでの日本を対象として、財政・金融・商業・流通などさまざまなトピックを扱います。論文講読と史料読解を通じて、卒業論文執筆の準備を進めます。 |
イノベーションの事例分析 |
本ゼミではイノベーションについて、実際の公刊データに基づいた事例分析を行います。過去には「猫カフェの経営戦略」、「音楽フェスビジネスの誕生と展開」、「アナログゲーム市場の成立」など各ゼミ生の趣味や関心をテーマにした事例分析を実施しています。 |
アジア経済史、アジア経済論 |
「アジアの世紀」と呼ばれる21世紀の世界経済におけるアジアの影響力の根源を探ります。日本を含む、アジア諸地域(東アジア、ASEAN諸国、南アジアなど)の相互関係を読み解き、歴史的視点から今日のアジア経済の姿がどのように形成されてきたかを考えます。 |
ファイナンス |
金融商品の仕組みと価格付けを中心としたファイナンス全般の知識を得ることを目標として、基礎的なテキストの輪読を行っています。輪読を通して必要な数学の知識、論理的な思考力、プレゼンテーション能力を養うことも目的としています。 |
行動意思決定論 |
人間の意思決定(将来に向けての選択)にどのようなバイアスがあるのかを心理学のアプローチで探求します。専門書を読んで知識を深め、ディスカッションで批判力を養い、個人やグループで自ら仮説を立てて心理実験をおこなって検証し卒業論文等にまとめます。 |
マーケティング・サイエンスによるデータからの知識発見 |
様々なマーケティングにかかわるデータが入手可能となっており、これらのデータに基づいたマーケティング上の意思決定をすることが大切となっています。本演習ではこれらのマーケティングデータを分析し、データに基づいて意思決定する方法を学びます。 |
財務会計 |
企業会計制度の構造とメカニズムに関する理解を深めることをねらいとしています。 |
管理会計に関わる研究テーマについて自分の手で研究を行うこと |
本ゼミでは、まず、研究を進める上で必要なデータ分析方法の基礎を身に付けます。次に、学生が主体となって具体的な研究テーマを設定し、グループで研究を進めます。最後に、グループで研究した内容について、他大学との合同研究発表会で研究発表を行います。 |
途上国における国際経営戦略 |
発展途上国における事業運営は、様々な点で日本とは異なります。そこには「定石」のようなものはまだありませんし、元になるデータも十分に整備されていません。そこで、基礎となる理論を学んだ上で、実際に現地を訪問し、データを集めて分析を行います。 |
マクロ経済学と金融論 |
インフレーション、失業、経済成長、景気循環など経済全体に関わる現象を研究するマクロ経済学と貨幣の役割やその存在意義、金融政策について研究する金融論の両分野を学びます。経済理論が複雑な現実の経済現象を考える上で、有用な思考的道具になることを実感してもらいたいと思います。 |
経営のプロフェッショナルになる |
経営戦略を構築し、事業の成長を図ったり、起業を行ったりする機会が飛躍的に増えています。本ゼミではそのための「戦略構築能力」をしっかり身に付けます。具体的には、企業の戦略分析や新規事業のビジネスプランニング、外部ビジネスコンテスト等への参加を積極的に行います。 |
マーケティング戦略 |
どんなに優れた製品やサービスも、顧客の支持を得られなければ生き残ることはできません。このゼミでは、顧客の必要に応えようとするマーケティングの基本的な考え方を学ぶとともに、具体的な事例分析や意思決定を通じて実践的な理解を深めます。 |
リスクとリターンの統合評価 |
将来の収益が確定しない金融商品の価格評価(プライシング)の考え方を理解し、使えるようになることを目指します。将来の収益は確率変数であり、投資はリターンだけでなくリスクも伴います。それらを価格という一つの指標に落とし込む工学的・経済学的技術を学びます。 |
テキストマイニング |
このゼミでは近年様々な分野で適用事例が増えているテキストマイニング(文書データの分析手法)について学習します。口コミ、新聞記事、報告書、歌詞、小説といった文書データを分析することで、その手法を理解し、活用する能力を身に付けることが、このゼミの目標です。 |
オペレーションズ・リサーチによる問題解決 |
オペレーションズ・リサーチは、現実世界の諸問題に対して、数学的手法やコンピューターを用いた科学的・合理的な意思決定を行う学問です。本ゼミではその理論と応用を学び、数理モデル、最適化理論に基づく科学的な問題解決、業務改善、意思決定に取り組みます。 |
ミクロ経済学・ゲーム理論 |
ミクロ経済学やゲーム理論、またそれらに関連する分野について学んでいます。3年生の間は、標準的なテキストを用いて、ミクロ経済学・ゲーム理論の基礎やそれらの応用について理解を深めます。4年生になると、それらの知識を基礎にして卒業論文に取り組みます。 |
マクロ経済学 |
日本のマクロ経済について勉強しています。 |
ゲーム理論を学ぶ |
本ゼミはゲーム理論を徹底的に勉強するゼミです。企業の競争や国の領土紛争から、サークルでの掃除当番の問題まで、政治・社会・経済におけるさまざまな問題をゲーム理論でモデル化し解く力を身につけます。 |