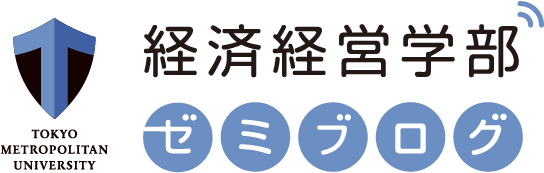皆さん、こんにちは。宮本ゼミ3期生の栗嶋佑太です。
先日、宮本ゼミはキャンパス周辺のゴミ拾い活動を行いました。
ゴミ拾い活動を通じて大きな学びが2つありました。
1つ目は、きれいな環境は当たり前でないということです。
自分の生活圏が汚いと感じている人は多くはないのでしょうか?実際、清掃活動前、 私はキャンパス周辺の綺麗さには自信を持っていました。
しかし大学周辺の小道には、空き缶、弁当のゴミ、タバコの吸い殻等が散乱していました。
一心不乱に清掃活動に励む中で、自分達と同じように清掃している人の存在に気づきました。自分は数時間の清掃でさえ疲れ果ててしまったのに、駅前にも、キャンパス内にも毎日のように清掃して下さる方々がいらっしゃいます。
今まで自分達が享受していた「当たり前」な環境は、こうした清掃活動に取り組んでくださる方々のおかげで成り立っていることを忘れてはいけないと感じました。
2つ目は、人がやりたがらないことからこそ学びが得られることです。
キャンパスに戻る途中、開始直後ゴミが落ちていなかったはずの道にゴミが散乱していました。ゴミ拾いの面白いところは、作業を始めてから段々と目に入らなかったはずのゴミも見えてくることです。
2時間も腰を下げて、下ばかり向いていて、手を汚しながら、ゴミを拾い続けると、
「こんな苦労しながら誰かが、誰かの捨てたゴミを拾っているのだ」と自分の視野が広がりました。
自分の手を汚しながらゴミを拾うなんて、普通はしたくないことです。
しかし、視野が広がったため、きれいな環境を維持するために日々作業されている方への感謝の気持ちを持つことができました。
今後の大学生活、あるいは社会に出てからも、誰も引き受けない仕事を拾って(ゴミを拾うと掛け合わせました笑)、常に感謝の気持ちを持ちながら、自己の成長を追求するために挑戦を続けていきたいと感じました。